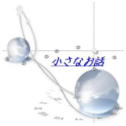すべからく世はこともなし・・・<3>
「 で、今年は?託生、どうするんだ?」
「そういうギイは?まぁ、対抗リレーは選ばれてるんだろうけど」
「パン食い競争!!!今日の分のリベンジも兼ねて、明日は存分に食ってやる!」
文化祭2日目の今日。
急遽、起こった(ことになっている)腹痛により、自室で大人しくしているギイの元を、
持てる限り出店のたこ焼きやら焼きソバやらを持ってぼくは訪ねていた。
「リベンジって・・・」
「だってな、何のために企画したと思ってんだ。ホットドッグ早食い競争!」
そこですか。
ブラックホールの異名ならぬ胃名を持つギイ君としては、今日の階段長企画
『ホットドッグ早食い競争』に参加できなかったことが、いたくお気に召さない様子で。
「笑うな、託生。食い物の恨みは恐ろしいって知らないのか?」
「知ってるけど」
「オレ、参加する気だったからさ」
「うん」
「どうせ食うんだったらウマいほうがいいだろ?」
「それは、そうだろうね」
「でな、街中の上手いって評判のパン屋でホットドッグ手配したんだよな〜」
心底、残念そうに云う。
「で、リベンジなんだ」
「けどな〜、そんなに食べられないけどな」
「まぁ、量を競う競技じゃないもんね」
「そ。先ず、予選だろ。で、準決があって、最後に優勝決定戦で、MAXでも3回、つまり3個しか
食えないんだけどな」
”しか”なんだ。ぼくだったら、3個”も”食べたら、充分なんだけど。
むしろ、多すぎるくらいだ。だって、パン食い競争って確か、昼食後直ぐ、だったはずだ。
「それも、味にこだわってあるの?」
「当然だろ。そこに、抜かりは、ないんだよ」
ニヤリと笑って云う。
そんなことを云いながらも、ギイの手は一向に止まらず、粛々と目の前のたこ焼きを
口に運び続けていた。
(ちなみに、焼きソバや回転焼き、その他諸々は既にその胃袋に収まった後だ)
「ふぅ、食った食った」
「満足、した?」
「ま、取り敢えずは、こんなもんかな」
取り敢えず、ですか。
相変わらずの食欲魔人っぷりに唖然としていると、
「後は、デザートだな」
「え?もう、ないよ。アツアツのたこ焼きとかと一緒に持つとアイスとか溶けちゃうとまずいと
思って買ってこなかった。欲しいんだったら、買って来るよ。ギイ、何がいい?」
「ちがう」
「え?ちがうって、なにっ・・・って、わわわわわっ」
ヒョイと抱き上げ高と思うとギイは、ぼくごとベッドにダイブした。
「ぎ、ぎ、ぎ、ぎ、ぎ」
「ぎぎぎ?」
くすくす笑いながら、首筋に唇を寄せる。
「ちょっ、ギぃっ。・・・ダメだって」
「ダメじゃない」
「だって」
「デザート、くれるんだろ?託生」
言葉の意味をスルリと変えてぼくに擦り寄る。
「そ、れは、そう云ったけど、って、ギイ。わわわ、ど、どこ触って・・・ってわわわわっ」
「色気がないのは相変わらず、だな。でも、オレ、もう待てない」
「だからって、わっ、ギイッ!どこさわっって-----!」
そっと、ギイの手がぼくのシャツの下から忍んできて、わき腹を撫で上げる。
「託生、デザート、プリーズ」
見慣れたはずなのに、いつまでも見慣れない美貌のどアップに思わずどっと赤面する。
その上、こんな風に無邪気な顔でニッコリ嬉しそうに微笑まれてしまったら、
抵抗なんて、出来る筈もなく。
「ごちそうさまでした」
「○△■×●□×▲ーーー!」
「お〜い、た〜くみ。たくちゃ〜ん」
ぷいと横を向く。
「たくちゃん、冷たい。・・・お前だって、嫌がってなかったじゃんか」
「抵抗できないように、したの、ギイだろっ」
思わず抗議の声を上げると
「抵抗できないくらい、ヨカッタ?託生」
「そ、そういうこと、云ってるんじゃないだろっ」
「オレは、ヨカッタよ。託生とこうしたかったから」
真顔で云われてしまえば・・・。
「・・・ぼくだって、それは・・・」
小さな声で答える。
ぼくだって、本当はいつだって、傍にいたい。
隣に君を感じていたい。
去年までは、当たり前で日常だったことが、今年のぼくらには難しいから。
多忙なギイが、何とか工面して捻り出された短くも貴重な時間がぼくらの逢瀬で。
だから、祠堂の中で、こうして昼間から二人っきりで過ごせるなんて、まるで夢みたいな話だと、
ぼくにだって解ってる。
思わず俯き唇を噛む。
と、両頬をそっと挟んで上向かせて視線を合わせる。
その淡い大好きなブラウンの瞳の奥が、まるで悪戯っ子のようにキラリと光ったような
気がした途端にニヤリと笑うと
「それはそうと。運動したら、腹が空いたなぁ」
う〜んと伸びをしながら云う。
「散々、食べたじゃないかっ!もう、お腹、空いたの?ギイ」
信じられない思いで云うと、カラリと笑って、
「散々って程も食ってないじゃんか。あ、デザートは堪能したけどな」
「堪能って・・・」
「ますます、欲しくなる程に」
「嫌だからね」
「わかってるって。それに、流石にそろそろ寮にも人が戻って来はじめるだろうしなぁ」
「ぼくも、そろそろ行った方が、良いよね?」
「いいじゃんか。文化祭の間の飯は全部!一緒に食う約束、だろ」
「そうだけど・・・」
「大丈夫だって」
余裕の表情で返される。
ウィンクも様になりすぎるくらい様になってて、思わず見惚れるぼくのことなんか、
すっかりお見通しのギイは
「こら、見惚れてんなよ、託生。そんな瞳で見られたら、とまんなくなるだろ」
そう云いながらも、不埒な気配を振り払うように、ぼくごと起き上がると、
「取り敢えず、シャワーでも浴びるとするか」
「あ、うん。ギイ先に浴びてきなよ。ぼくは、後でいいから」
身体中のそこかしこに残る甘い余韻のお陰で、まだ、すんなりとは動けそうもないから。