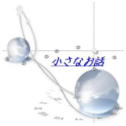名前を呼んで・・・
〜Name is called〜<3>
強化レッスンを終え、ようやく祠堂学院に戻るという前日、赤池君から電話があった。
「葉山、落ち着いて聞いてくれ。ギイが記憶喪失になった。僕達のことは勿論だが、
家族のことも、そして葉山。お前のことも何も覚えていない」
「え?」
思いもかけない連絡に驚いて、そして・・・。
どうすれば、いいのだろう。
どうすることが、いいのだろう。
この機会に、ぼくはギイを、ギイの手を離した方が良いんじゃないだろうか。
特になにか特別な取柄がある訳でも、なんでもない。
ほんの少しバイオリンが弾けるっていうだけで、それだって、ぼくくらいの腕前なら
他にも沢山いるだろう。
どこから見ても平凡で、そしてそのくせ、厄介な過去のあるぼく。
過去のことを抜きにしても、とてもギイに釣り合ってるとはお世辞にも云い難い。
それに、第一。
そもそも、今のギイがぼくに会って、ぼくなんかを想ってくれるとは思えない。
またぼくを愛してくれるとは、とても思えない。
ぼくのことを知らないでいるギイに、もう一度、一から過去を話すなんて、出来ない。
そう思うと、寒くもないのにブルリと身体が震えた。
そのまま、ズルズルと壁に背を持たせて座り込む。
立っていられなかった。
ギイを失うかもしれない。
足元から全てが崩れ去っていくような感覚にゾッとした。
祠堂に戻ったぼくは、ギイの部屋をまだ訪れられずにいた。
怖くて行けなかった。
近づくことすらできなかった。
もう少し、覚悟を決めてからでないと、とてもじゃないが堪えられそうもなかった。
ギイを失う覚悟をしないと、いけないのかもしれない。
「なあ、葉山。いつまでも逃げてるわけにはいかないんじゃないか?そりゃあ、
あれだけお前さんにベタボレだったギイがお前のことも覚えてないのはショックだと思うがな」
「それは、いいんだ」
「え?いいのか?」
「うん、いい」
即答したぼくに章三は不思議そうにぼくの顔を覗き込んだ。
「ふむ。無理して強がってるって訳じゃないみたいだな」
「うん、それはね、大丈夫なんだ。というか、仕方ないことだと思うしね」
そもそも不可抗力なんだし。ギイは被害者でこそあれ、何も悪くなんかない。
「じゃあ、なんだ?」
「だってさ、世間的に、一般的に考えてさ。男同士のぼく達は受け入れられることは
少ないというか、難しいよね」
「まぁ、それはそうだが・・・」
「それに、ギイも、基本的には女の子が好きな訳だし」
去年、佐智さんの別荘でビオラの人の大学の話しになって、”そそるような美女が多い”とか
なんとか、云ってたギイ。
「で?」
「だったら・・・」
ぼくの言葉を促す章三の目が探るようにぼくを見る。
だったら、このままぼくとのことは忘れて無かったこととして生きていく方が
ギイの為には良いんじゃないかと思ったのだ。
色々、ぼくとしてはこれ以上考えられないというくらいに考えた。
そして思ったんだ。
ある意味、今回のことはギイにとってチャンスなんじゃないかって。
「葉山・・・」
「だから、ぼくのことは、ぼくとのことはギイには伝えないで欲しいんだ」
「葉山は、いいのか?それで」
「いい」
ぼくはキッパリと云い切った。
今は辛いけど、心が引き千切られてしまったように痛いけど。
それでギイが幸せな光の中を歩んでいけるというなら、そんなのは一体
何ほどのものだというのだろう。
ぼくにとって、ギイが幸せに微笑んでいられるのなら、それが何よりの幸せだ。
それに、祠堂学院に入学して、避けていた1年の時さえも、ギイはぼくに
あたたかな幸せをたくさんくれた。
それだけで、もう充分だ。
たとえ、ギイが覚えていなくても、ぼくは覚えている。
心の中の引き出しを、全部ギイとの幸せの思い出で埋め尽くして、時々それを
取り出して眺めながら生きていける。
だから、ぼくはギイの手を放そうと決めた。
その決断に賛成かと云われたら、正直とても複雑だった。
感情的に云うなら、葉山の決断は間違っていると思う。
けど・・・葉山の立場にたって考えると、きっと、僕もそうするだろうと思った。
だから、何が正解なのか僕には解らなかった。
厄介な、ある意味とてつもなく厄介なバックボーンを僕の相棒は抱えている。
恐らくは、僕が知る以上に考える以上に語られていないそれらには、
とてつもない厄介さがあるだろうと思っている。
何もかもを知る必要は無いから、そんなもの無くても僕は奴を信じているし、
奴を認めているから、敢えて訊かないが。
例えばそれらは、きっと、女の子でも厄介過ぎるシロモノだろう。
ましてや、葉山は男だ。
葉山が臆して決めたことなら、それは”逃げ”だと糾弾もしたかもしれない。
でも、違うのだ。
葉山は、葉山託生というやつは、本当にどうしようもないお人好しだと僕は思う。
アイツは、ただただギイの幸せだけを願ってこの決断をしたんだろう。
「それじゃあ、葉山の、お前自身の幸せはどこにあるんだよ」
それでも、そう責めた僕の言葉に、寂しそうに、でもキッパリと云い切った。
「ギイが幸せでいてくれることが、ぼくにとって一番の幸せなんだ」
そうして、儚げではあったけれど、穏やかに幸せそうに微笑んだから、
僕はそれ以上何も云えなかった。