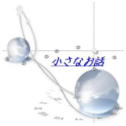想いをのせて・・・<2>
「だってさ、お前、バイオリンで語るだろ?佐智もそうだけどさ」
「え?」
「だーかーらー。佐智は確信犯だから仕方がないとしてさ、お前なんか無自覚だからな〜」
続く言葉に益々訳が解らない。
「ま、そこが好いっていうか、だからこそというか、だな」
「うん?」
「お前が真剣に演奏してるの聴いてたら、ガンガンに伝わってきちゃう訳だ。お前の気持ちとかさ」
つまり、それって・・・。
「勿論、その音楽そのものに没頭してる時もあるけどさ、そうじゃなくてさ、
オレに聴かせてくれてる時な」
「わ〜、タンマ!ギイ。止めて、解った!云わなくていい!!」
「お前がオレをどう想ってくれてるか、どんなに深い想いをもってくれてるか伝わってくるんだ」
「それはっ、ギイッ」
焦るぼくにお構いなしにギイの言葉は続く。
「嬉しいんだけどさ、勿論それってめっちゃくちゃ嬉しいんだけどな」
けど?迷惑だった?ギイ、嫌だった?不安に思っていると、違うよというように微笑んで
「違うって。変な心配するなよ、託生。そうじゃなくてさ、オレ、嬉しいのと同じくらい
悔しいっていうか、羨ましく思うんだよ」
「え?」悔しい?羨ましい?何それ?およそギイらしくない言葉だ。
「オレは知っての通り、音痴だし、音楽に関しては聴く専門でさ。コレばっかりは、どうも相性が
合わないっていうかさ。況してや、そこに想い、とか心を乗せるなんてこと、とても出来ないしな」
確かに、リズム感はいいのに、何故だかギイは音程と相性がすこぶる悪い。
「託生のように自分の気持ちを自然に”音”に乗せて伝えられたらって思うんだよ」
「そんなに、わかっちゃう?」
「ああ、バッチリ」
うわ、今更ながら恥ずかしさがこみ上げてくる。
「で、いっつもオレばっかり、こんなに幸せな思いさせて貰ってさ。この気持ちを託生にも
感じさせてやりたいって思うんだ」
「ギイ」
「すっげ、幸せな気持ちになるんだ。静かに奥深くから染み渡るように染込むように
託生の想いに包まれてさ。満たされてくんだ」
「・・・ギイ」
「だからさ、出来ることならさ、託生、お前にもこういう想いをさせてやりたいなって
思うんだけどさ」
「ギイ」
「代わりにオレに出来ることっていったら、素直に心に思ったことを、
言葉に現すことくらいかなってさ」
”素直に言葉に表す”ぼくにとっては、その方がよほどの難題なのだけれど。
「あ、伝えずにはいられない気持ちになるってのも、あるけど」
「ギイ、ありがと」
「オレの方こそ、ありがとう、だ」