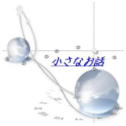遊奏舎 HP
トクベツのキミと・・・<2> 〜キミだけが、ぼくのトクベツ after2〜
「あ〜、つまりな。託生のせいじゃないことは、オレも重々承知はしてるんだがな」
部屋へ着き、二人してソファに並んで腰掛けると、前髪をクシャリと掻き揚げながら、
ギイが話し出した。
「うん」
「だが、しかし。面白くないもんは、面白くないんだよ」
「へ?」
「だーかーらー!!」
ぐいとぼくを立たせると、スッと背後に回ってぼくを抱きこむように目隠しをする。
そして、耳元で「だ〜れだ?」
「ギイ?」
背中にギイの体温を感じながら耳元で囁かれ、背筋がゾクリと泡立つ。
ドキドキしているのを悟られたくなくて、なんでもない風を装う。
「あのね、このシチュエーションで目隠しされて誰だ?って訊かれたら,
いくらぼくが鈍くたって、判るに決まってるだろ」
しかも、ギイをぼくが間違うはずないのに。
とは、云わないけど。
「判ってるって。このシチュエーションでなくても、託生がオレを間違う訳ないってことも」
そのまま、背後からぼくを身ぐるみ抱きしめながら、肩口に額を押し付けギイが呟く。
「オレじゃなくても、知ってる奴のことなら、託生なら、ちゃんと聞き分けて、そいつが
誰なのか当てるなんて造作もないことだってことも・・・」
それが、どんなにソイツを喜ばせることになるのかなんて、きっと思いつきも
しないんだろうけどな。
「ギイ?」
「けど、オレは面白くないんだよ」
「ギイ、それって・・・もしかして、ヤキモチ?」
「悪いか。そうだよ、ヤキモチだよ!」
云うが速いか、クルリとぼくを反転させられ今度は正面から抱きしめられた。
「べたべたべたべた、どいつもコイツも・・・」
「ギイ?」
「目隠しだなんだと、ここぞとばかりに、託生に触りまくりやがって。
託生に触っていいのはオレだけだ」
そういうと、更にぎゅうっとぼくを抱きしめる。
「っぷ」
「こら、笑うな」
「だって・・・」
「わ〜ら〜う〜な〜」
そういうギイの声も笑い声だ。
「もう、ギイってば」
そう云いつつも、恋しい人のヤキモチは、ぜこんなも胸を甘く疼かせるのだろう。
「どうせ、な。オレは狭量ですよ。けどな、嫌なもんは、嫌なんだよ。仕方がないだろ」
「開き直ってる」
「悪いか」
「悪くは、ないけど」
「けど?」
「けど、それより、ぼくにキスする方が建設的、なんじゃない?」
するりと、そんなコトバがこぼれた。
その言葉にギイもハッと目を見開いた。
けど、それも一瞬の事で。
「それもそうだな。じゃ、お言葉に甘えて・・・」
ニヤリと不敵な笑みを浮かべてギイが唇を寄せる。
ぼくだって、いつも望んでいるのは君だけだから。
他の誰でもなく、ギイだけだから・・・。