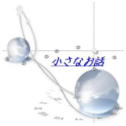名前を呼んで・・・
〜Name is called〜<2>
遡ること、1時間ほど前。
一部始終を見ていた矢倉によると、1人、グランドの脇を走っていたオレへ、サッカーボールが
横からマトモに直撃・・・したらしい。
運悪く、自分の走っていた勢いも加わって受け身を取ることも出来ずに倒れたオレは頭を花壇に
植えられていた金木犀の根に強打した・・・らしい。
そして、意識を取り戻した時には綺麗さっぱり記憶が消えていた、という訳だ。
「校医の中山先生からも説明があった通り、君の名前は<崎義一>通称ギイ。
この祠堂学院高校の3年。そして、全寮制のこの寮の3階の長、階段長という役を担っている」
「ああ、らしいな。で、それと外出禁止の因果関係が解らないんだが・・・」
「自分の素性も解ったんだろう?」
「ああ、聞いた。全然実感ないけどな」
言葉としては理解できていても、本当に実感が伴わないのだろう。
ギイにしては珍しく察しが悪い。
「だーかーら!取り入ろうって輩がうようよいるところに、そんな状態のお前を放り込んだが最後。
しっちゃかめっちゃかにされっちまうのは明白だろうが!色々と面倒が起きないように、
大人しく自室待機してろってことだ」
元生徒会長だという日本人にしてはやや色素の薄い柔和な表情の学生が冷静に話し始めたところに、
強引に割って入った1階のオレと同じく階段長だという矢倉柾木と名乗った学生が一息に云う。
「僕達に出来ることはサポートしてやるが、それにはギイ本人の協力が必要だ。どうせ、お前の
ことだから、自分ひとりで抱え込もうとするんだろうが、今回はそうはさせないから、そのつもりでいろ」
風紀委員長をしていたという赤池章三が言い放った。
「矢倉も赤池もそのくらいにしておけ。今の崎に当たっても仕方がないだろう」
まぁ、当たりたくなる気持ちも解らなくはないがな。と仕方がないなというようにふっと笑うと、
三洲が重ねて云う。
「崎、お前が望もうとそうでなかろうと、一歩出れば間違いなく厄介ごとに巻き込まれる。
しかも、これもお前が望もうと望むまいと・・・ここにいる連中・・・正確には他にもいるが・・・
お前をガードしようとするだろうな」
今ひとつ、オレを取り巻く人間関係は解らなかったが、それでも、ここにいる連中が信用するに
値する人間だという事は解った。
どの瞳も、本気でオレを心配してくれていた。
2日もすれば、この生活にも慣れてしまった。
昼間も必要以上には自室である300番からは出る事なく、しかも、殆どの場合、誰かしら3年の
しかもこの祠堂学院の中枢メンバーがいる。
いてくれている。
全く不安が無いといえば嘘にはなるが、取り返しのつかないような事にはならないだろう
という感覚があった。
だが、今のところ、全く記憶が戻る気配はなかった。
思い出せない事に歯痒さを感じる事はあったが、この連中とならいっそこのまま、
これから新しい思い出を作っていくのも悪くはないかと思えてきて、そう思えてしまえば、
それこそ大きな不安はなくなる。
ただ、どこかに何かを置いてきてしまったような、漠然とした喪失感があった。
思い出せない事で、自分という存在を失ったような、感覚からくるものと、それ以外に、
いやそれ以上に、欠けている何かを追い求める焦燥感のようなものに襲われる事があった。
だが、考えても考えても、それが何なのかが解らない。
必要なものなら、嫌でも思い出すだろう。訳の解らない事にこれ以上捉われていても時間の無駄だ。
そう頭を切り替え何するでもなく外を見る。そろそろ、誰か・・・。
恐らくは矢倉辺りが来る頃だろうと時計を見る。
「いよっ。ギイ。調子はどうだ?何か思い出したか?」ビンゴだ。
相変わらずの明るい調子で矢倉が部屋に現れた。
「いや、特に何も・・・」
「そっかぁ」
「ああ、悪いな」
「俺は良いんだけどさ。思い出ってのがないって、寂しいだろうと思ってさ」
「どうなんだろうな。今のところ、そう不自由は感じないけどな」
「ふうん、そんなもんか」
「まぁ、家族と会った時にでも、感じるのかもな」
1年の同室者でもあったという赤池章三の話によると、親父とお袋、そして大層可愛がっている妹が
いるらしいのだ。だが、生憎とそれらも全く実感は無かった。
「家族、ねぇ」
「なんだよ」
「いや、なんでも・・・」
このところ、矢倉に限らず、こんな会話がよくあった。
「あ、矢倉も来てたんだ」
「野沢か」
「うん?どうしたのさ。何の話?」
「ああ、相変わらず記憶は戻らないって話をしてたんだ」
「へえ、で?」
「で、だからといって今のところ不自由はないんだが、家族と会った時には思い出せないことに
寂しい気持ちになるのかもしれないなぁとね」
「家族、ね」
まただ。
「なんだよ」
「なにが?」
「矢倉も野沢も、なんだって<家族>ってところに拘るんだ?」
「拘ってるって訳じゃないんだけどな」
「うん。拘ってるっていうかさ・・・。ね、ギイ」
意を決したように野沢の表情が引き締まった。
「もしかしたら、<家族>より大事、か・・・もしくは、同等の大切な存在があったって
いうような感覚はない?」
「どういう意味だ?」
「本当に思い出せないことに全然不自由も寂しさも感じてないのか?」
矢倉も真摯な顔で訊いてくる。
それは、自分自身でも訳の解らないこの喪失感や焦燥感の事を云っているのか?
「お前等、何が云いたい?何を知ってる?」
だが、どんなに尋ねても、誰もそれ以上の事は云おうとしなかった。