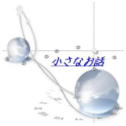名前を呼んで・・・
〜Name is called〜<Fine>
ギイ、本当に?本当に帰ってきた?
「ああ、そうだよ、託生。帰ってきた。だからお前もオレのこと、呼んでくれよ。
いっつもみたいにギイって呼んでくれ」
「ぎ、ぃ」
「託生・・・」
「ぎい・・・ギイ、ギイ、ギイ!!」
瞬間、身ぐるみ総てを包み込むようにギイに抱きしめられていた。
「ごめんな、オレ、お前のこと」
「ギイ」
最後まで云わせたくなくて、ぼくも精一杯腕を伸ばしてギイを抱きしめた。
抱きしめ合って、見つめ合って・・・やがてギイの唇がぼくの唇に落ちてきた。
そっと、優しく。
・・・・・深く、深く・・・。
「託生、ごめんな。オレのこと、いや、オレ達のことを諦めさせるところだった。
ごめんな、不安だったろ?」
「ぼくこそ、ごめんね。勝手に一人で決めてしまおうとして・・・」
「託生が謝ることなんかないだろう。そう思ったのは、オレのことを思ってだってことは
解ってるから。ごめんな、不安だったろ。寂しい思いさせたよな」
「ギイ・・・大丈夫、だった、よ」
本当は全然大丈夫なんかじゃなかったけど、すごくすごく不安で寂しかったけど、
そんなのギイには知られたくなかった。
知ったら、ギイはまた自分を責めるのが解っていたから。
「託生、お前。本当に嘘吐くの下手だな。解ってる」
「そんなこと、ないってば」
「解るよ」
「だって、本当にだいじょ」
「解るんだ。・・・オレもあの時そうだったから」
あの時、あのNYでのぼくの記憶喪失・・・
「あ・・・」
「違う、責めてるわけでもなんでもないからな」
「ごめん、ギイ」
そうだ、先にギイを忘れて、しかも拒絶したのはぼくだ。
あの時、ギイもこんな気持ちだったのだろうか・・・。
「ごめん。ごめんね、ギイ」
「だから、違うって。それに、託生、ちゃんと帰って来てくれたじゃんか。帰って来てくれた時、
オレ、めちゃくちゃ嬉しくて、心の中、全部が喜びで一杯に満たされたんだ」
「ギイ、ごめんね」
「だから、託生、もう・・・」
「ありがとう」
「託生?」
「ありがとう、ギイ。帰って来てくれて、ありがとう」
この喜びを他にどう伝えていいのかわからない。
ギイがギイの意思で帰って来てくれた。
「ばか、当たり前だろ。オレとお前は世界最強の恋人同士なんだって、いつも云ってるだろ。
どんなことがあったって、回り道したってなんだって、絶対。絶対に帰ってくるから。
だから、託生。お前も、なにがあってもオレと一緒に、オレの傍に在ってくれ」
「うん、うん。ギイ・・・」
「ありがとう、託生」
「ありがと、ギイ」
そうしてぼくらは、しばしの間、バカみたいに抱きしめあって見つめあって、互いの名前を
呼び合って『ありがとう』と繰り返して・・・それがいつの間にか『愛してる』に変わって・・・
幾度となく啄ばむような口付けを交わして・・・絡め合ってもう、どちらがどちらの吐息か
わからなくなる頃。
ふわりと抱き上げられてそっと、まるで壊れ物を扱うように優しくベッドに降ろされ、
そっと前髪を掻き揚げられて、瞳を開けると、そこには優しいぼくの大好きな透き通った
ような黄水晶のようなギイの瞳があった。
ジッと見つめられて、気恥ずかしくて思わず視線を彷徨わせると、クスリと微笑む気配がして
「ああ、やっぱり託生だ・・・あのな、三洲がな・・・」
ぼくの耳元で囁く。
瞬間、思わず耳までかぁっと朱に染まるのを自分でも感じた。
云われた時は”まさかな”って思ったんだけどな、とギイが苦笑する。
『崎、加減というものを考えろよ。だが、まぁ後のことは気にするな。借りが追加になるだけだ』
「と、云うわけだから、託生。点呼のこととかな、そういう諸々の心配は三洲が引き受けてくれた
からな、安心しろ。これ以上、一つや二つ借りが増えたところで今更たいした違いはないさ」
そうニヤリと笑うと有無を言わさず口付けた。
…Fin…