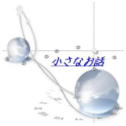独りで寂しくなんてならないで・・・<3>
【外出中】の札をノブに掛けて戻ってくる。
ふわり
まるで壊れ物を扱うように、そっと柔らかに胸に抱きこまれた。
花の香りに包み込まれて、ホッとした。
と、同時に泣きたくないのに、涙が溢れてきて、零れてしまいそうになって、
何とか堪えようと目をしばたかせる。
「託生、オレには隠さなくて良いんだ。いや、違う。隠さないでくれ。
涙も。堪えなくて好いんだ」
「ギ、イ・・・」
思わず見上げると、眼鏡はいつの間にか外されていて。
そこには優しい大好きな薄いブラウンの瞳があった。
ゴメンね、ギイ。
普段、自身のバックボーンを連想させる話は極力しないようにしているギイ。
なのに、あんなに大勢がいる場所で、サラリとそれを想像させるようなことを口にしたのは、
きっと、絶対、ぼくの為で。
聡いギイ。きっとぼくが密かに追い詰められていたことに、気付いて助けてくれた。
みんなの悪意からではない、純粋な好奇心という名のむしろ好意さえ含んだ言葉の数々に、
ぼくが勝手に追い詰められてただけなのだけれど。
ぼくをみんなの視線からスッと庇ってくれた背中にホッとした。
あの、二年生の春の入寮日。
外の冷たい風から、僕を守るように閉じられた窓。
あの時から、ずっとぼくは守られてる。
「なに?託生?」
こんなにも優しい声で囁かれて逆らうことなんて出来るわけもなく。
「話して、どんなことでも」
ましてや、こんな風に懇願するように云われてしまえば。
「ぼく、本当に、虫歯。ないんだ」
「ああ」
「あのテレビで云ってた理由といっしょなのかとか、なんて、それはわかんないんだけど・・・さ。
実際に、ぼくには両親からそんな風に食事の時に分け与えられたことってなくて・・・」
それで、と視線で促されて、ぽつりぽつりと話していく。
「でも、兄さんには、虫歯、あったんだ」
毎年のように、長期休暇には虫歯治療に通っていた。
ぼくも一緒に連れられて、歯医者に通ってたんだ。
呟くように、そう話す託生を見ているだけで胸が締め付けられる。
淡々と話す姿に、却って胸が痛い。
いっそ、泣いて喚いて取り乱してくれたなら、こんなにも切なくなりはしないだろうに・・・。